

その縄張りの中につくられたという「福山城」へ。
もともとの福山城には存在せず、
福山駅からの観光客のためにつくられた階段を上る。
駅構内を撮影。左奥の7・8番のりばは
2011年3月にも利用した福塩線のホーム、
長い5・6番のりばと隣の3・4番のりばは山陽本線ホーム。


伏見櫓(国指定重要文化財)が迎えてくれる。
水野勝成が大和郡山からの転封に際して2代将軍
徳川秀忠から拝領して移築したといわれている。

福山城本丸の正門として使われていた。
これも伏見城から移築されたものといわれている
(現地の説明板にも記されている)が、
二の丸正門の鉄門と混同されているとの指摘
(参考サイト:備後歴史探訪倶楽部)もある。
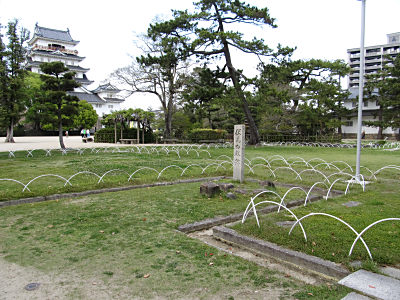

前出の備後歴史探訪倶楽部のページでは、
本丸御殿は近世において「伏見御殿」と称されておらず、
また御殿も伏見城から移築されたのは一部であると
指摘されている。


城下や近隣の村に「時の鐘」を告げ、
また緊急時に藩士を招集する太鼓も備えていた。
櫓が補修を重ねた結果原形をとどめなくなったため
昭和54年の復元工事の際に銅板葺きに改めた。


原始時代から明治時代までの福山の歴史に関する
資料が展示されている。




残っていない。










向かって左側に出入口があったが、埋められている。
右奥は鐘櫓。


日米和親条約を締結した阿部正弘の銅像。
藩主としては新たな藩校・誠之館の設置を行っている。


右奥にはかつて神辺二番櫓があった。
遺構らしきものは見当たらなかった。




天守の礎石。

天守の礎石と再建天守を見る。
見学予定の広島県立歴史博物館は
入館が16時30分まで、閉館は17時なので、
いったん福山城跡探訪を中断して
県立歴史博物館へ向かった。
<その2に続く>