中央本線鳥沢→猿橋
Chūō line Torisawa→Saruhashi
[山梨県大月市]
![]() ホリデー・パスの旅2010
ホリデー・パスの旅2010
中央本線鳥沢→猿橋
Chūō line Torisawa→Saruhashi
[山梨県大月市]
2010年5月3日
|
世間一般で「ゴールデンウィーク」といわれる5月1日~5日、行楽地はどこも人が多すぎるだろうということで、「ホリデー・パス」(2300円)を使って近場へ日帰りで行くことにした。 登戸駅で「ホリデー・パス」を購入。早速使用開始すると、南武線で終点の立川へ。 |
||
 |
終着駅・大月の2つ手前、鳥沢駅で下車。 | |
 |
このあたりは甲州街道の宿場「下鳥沢宿」だったところ。 進行方向右側はともかく、左側には宿場町の雰囲気が残っているような気がした。 |
|
 |
「大月総合体育館入口」交差点に到着し、周囲を見渡すと、目当てのものは国道20号の進行方向右手にあった。 | |
 |
かつて中央本線が桂川の左岸を通っていた時に、ここには甲州街道をオーバークロスする陸橋が架かっていた。 その橋はすでに撤去されているが、橋台が1本残っていた。 |
 |
 |
というわけで、鳥沢から猿橋までは、中央本線の旧線を辿ってみる。 事前に見た情報は『新・鉄道廃線跡を歩く2』とYahoo!JAPANの地図をプリントアウトしたもののみ。 なお、鳥沢方には橋台およびその痕跡らしきものは見つからなかった。 |
|
 |
橋台の先にも旧線のものと思われる築堤が続いていた。 左下の画像の階段を上がった先には右下のような木柱があったが、これも鉄道がらみだろうか。 |
|
 |
 |
|
 |
このあたりは斜面の崩壊によるものか、土砂に埋まってしまっている。 | |
 |
公園のような部分から鳥沢方を見る。 | |
 |
同じ場所から猿橋方を見る。 地元民の裏庭のようになっている。 |
|
 |
猿橋方へ進んでいくと、行く手には藪が待ち受けていた。 | |
 |
藪に突入する前に鳥沢方を振り返って撮影。 | |
 |
覚悟を決めて藪に突入。 竹などを掻き分けていくと、奥のほうにかすかに「それ」らしきものが見えた。 |
|
 |
最後の「自然のバリケード」を右側から強引に通り抜けると・・・ | |
 |
中央本線旧線・第1富浜トンネル(鳥沢方)。 | |
 |
近づいて撮影。 | |
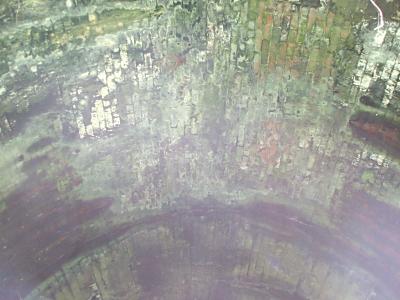 |
天井はこのようになっている。 | |
 |
金網の目からカメラで内部を撮影。 | |
 |
←進行方向左側にあった穴。 何が埋め込まれていたのだろうか。 銘板が打ち付けられていたと思われる部分。→ |
 |
 |
トンネル前から鳥沢方を見る。 | |
 |
引き返す前に、鉄道と関係ありそうな石柱を発見。 | |
| 来た道を戻って国道20号に復帰し、旧線を右手に見ながら歩いていく。 バス停を過ぎて分岐を右折し、エクスクラメーションマークの分岐も右折すると、突き当たりには富浜公民館 そこからさらに右へ行くと・・・ |
 |
|
 |
中央本線旧線・第1富浜トンネル(猿橋方)。 |  |
 |
第2富浜トンネルの鳥沢方は立ち入ってよさそうな場所からは確認できなかった。 (帰宅後に調べてみたら、造成工事で埋められてしまったらしい。) |
|
 |
トンネルに近づいてみる。 藪に覆われた鳥沢方と違い、猿橋方は容易に近づくことができる。 |
 |
 |
ただ、その分入口には金網に加えて有刺鉄線が張られている。 | |
 |
銘板が打ち付けられていたと思われる部分。 | |
 |
天井。 蒸気機関車が吐き出していた煤のせいか、 黒くなっている。 |
|
 |
金網の目からカメラで内部を撮影。 | |
 |
トンネル前から猿橋方を見る。 | |
 |
トンネルの手前には小さな沢があり、橋が架かっていたが、この橋はいつから架かっているのだろう。 | |
| エクスクラメーションマークの分岐まで戻り、今度は左側の道を進む。 途中から舗装がなくなった道を進むと・・・ |
||
 |
宮谷川に架かっていた橋の橋台が現れた。 |  |
 |
川の中に立つ橋脚も健在。 |  |
 |
その延長線上には、かなり小さいが宮谷トンネル(鳥沢方)が見える。 |  |
| 第2富浜トンネル(猿橋方)は橋台の上にあるようだが、全く見えないし、登ろうにもアプローチルートが見当たらないため断念。 獣道を通り、八ツ沢発電所三号水路橋を見てから国道20号に復帰。 |
 |
|
 |
「宮谷入口」交差点付近。 |
|
 |
宮谷トンネル(猿橋方)もすでに埋められているが、なぜかポータルの一部だけ出ている。 |  |
 |
中央本線が通っていた跡と思われる場所は均されて空き地(駐車場?)になっている。 |  |
 |
国道20号沿いに歩いて、空き地の反対側に回った。 | |
 |
大原トンネル(鳥沢方)があるといわれる場所。 構造物はあるが、これはまちがいなくトンネルではなく(甲州街道をオーバークロスしていた)陸橋の橋台。 見上げてみたがトンネルは見つからなかった。 (帰宅後に調べてみたら、築堤跡あたりからだと橋台の上に見えるらしい。現地でそこに気づかなかったのは残念。) |
 |
 |
それでも「宮谷入口」交差点で撮影した画像に写っていないかどうか見たところ、それっぽいものが写っていた。 その部分だけ切り抜いてみたが、他サイトのトンネル画像と比べるとどうも違うような気がする。 |
|
 |
猿橋中学校入口を過ぎて、分岐を右折すると気になる構造物が。 まちがいなく大原トンネル(猿橋方)だろうと思い撮影。 |
|
 |
ここからは降りられない。 もう少し歩いて階段を下りると・・・ |
|
 |
日本三奇橋の1つ、猿橋。 |  |
 |
ただし、このアングルでは普通の木橋にしか見えない。 | |
 |
猿橋から見る桂川渓谷。 | |
 |
下流側に見えるのは、もしや中央本線旧線の橋が立場川橋梁(信濃境-富士見間の旧線区間に残る橋)のように残されているのか?と思ったが、説明板によると八ツ沢発電所一号水路橋だった。 ※立場川橋梁は6年後の夏に青春18きっぷを使って訪れている。 |
|
 |
猿橋を南側から撮影。 このアングルなら、猿橋が三奇橋の一と云われる由縁が分かるはず。 |
|
| 八ツ沢発電所一号水路橋を南側から撮影。 |  |
|
 |
さまざまなアングルで猿橋を撮影。 |  |
 |
 |
|
 |
「展望台」と称する場所から撮影を試みた。 ←猿橋と水路橋|水路橋と桂川渓谷→ 今の季節は、この場所から猿橋を撮影するには向かなかったようだ。 |
 |
 |
「展望台」と同じレベルから桂川(上流方向)を撮影。 河川敷にはキャンピングカーが2台止まっているのが見える。 |
|
 |
山梨県道の新猿橋(左画像)。 ここからも猿橋を右画像のように眺めることができる。 |
 |
 |
国道20号の新猿橋へ回ると、大原トンネル(猿橋方)の上部が見える。 晩秋になって葉が落ちたらトンネル部分が見えるかもしれない。 |
 |
 |
国道20号の新猿橋から水路橋と猿橋を見る。 | |
 |
桂川の南岸(右岸)では、なんとレンガ造りの橋台の上に家が建っていた。 |  |
 |
猿橋見物と中央本線旧線探索を終え、大月市立郷土資料館へ。 その途中には、約6000年前に富士山から流れ出てきた溶岩流による地層が見えていた。 中央部には柱状節理が発達している。 |
|
 |
大月市郷土資料館。 だが、展示されている郷土資料はあまり多くない。 |
|
 |
歩いて猿橋駅へ行く途中に見かけた、廿三夜塔と道祖神の祠。 | |
 |
猿橋駅に到着。 自動販売機のそばにある時刻表を見ると、次の下り列車は13時21分発の甲府行き。 時計を見ると13時20分。まもなく下り列車の来る時間。 そしてホームの方向を見ると、まさに甲府行き普通列車が入線するところだった。 慌てて階段を上がり、改札を通ってホームへの階段を降り、何とか間に合った。 |
|
大月駅へ→
![]()